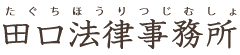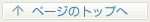離婚・男女問題

離婚は、結婚の倍以上のエネルギーを要する、と言われています。離婚をするにあたっては、子どもの親権、養育費、財産分与、慰謝料等、解決しなければならない問題がたくさんあります。
離婚をどのようにして進めていくべきか、離婚の条件や相場、慰謝料や養育費、財産分与、子どもの面会交流、年金分割等、離婚に関する様々な事柄について、経験豊富な弁護士が、アドバイス・サポートさせていただきます。
【離婚】
離婚の手続
1 協議離婚
協議離婚とは夫婦の合意による離婚をいいます。離婚に至る理由や原因は問いません。
協議離婚を行うには、当事者間の合意のほか、協議離婚届出書を提出することが必要です。
2 調停離婚
協議での離婚ができない場合、離婚自体には合意していても、親権、養育費、財産分与等の条件で合意ができない場合に、家庭裁判所に調停離婚を申立てることができます。
調停では、調停委員の関与のもと話し合いが進められ、離婚や離婚条件について合意に至れば、調停離婚が成立します。
なお、離婚については、離婚訴訟を提起する前に、まず、家庭裁判所に調停の申立てをすることが必要となります(調停前置主義)。
3 審判離婚
調停で離婚が成立しなかった場合、離婚の審判がなされることがあります。もっとも、審判離婚はあまり行われていないのが実情です。
4 裁判離婚
訴訟による離婚手続です。
①配偶者の不貞行為
②配偶者から悪意で遺棄されたとき
③配偶者の生死の3年以上の不分明
④配偶者の強度の精神病
⑤その他離婚を継続し難い事由
(民法770条1項所定の離婚原因が存在することが必要です。)
離婚原因
協議離婚や調停離婚はあくまで話し合いでの離婚であり、離婚が認められるために、法律で定める離婚原因は必要ありません。これに対し、裁判離婚の場合は、夫婦の一方の請求に基づき、法律上の制度である婚姻を解消させる制度であることから、法律で定められた離婚原因が必要となります。法律で定められている離婚原因は以下のとおりです。
①不貞行為
②悪意の遺棄
③3年以上の生死不明
④強度の精神病にかかり、回復の見込みがないこと
⑤その他婚姻を継続し難い重大な事由
親権
1 夫婦に未成年の子がいる場合、夫婦のどちらかが親権者になるかを決定しなければなりません。どちらが親権になるかは、まずは話し合いで決めますが、話し合いで決まらない場合には、家庭裁判所に調停を申し立てることが可能です。
2 親権者・監護権者指定の判断基準
裁判所が判断する場合、子に対する愛情の度合い、親の年齢、健康状態、資産、経済力等の父母の事情、子の年齢、性別、子の意思、発育状況等の子の事情を総合的に考慮して親権者が決められますが、裁判所が重視していると考えられるのが以下の事情です。
①継続性の原則
これまで実際に子を監護してきた者を優先させるという考え方です。
ただし、勝手に連れ去った等の場合には不利な事情となります。
②子の意思の尊重
15歳以上の未成年の子について、親権者の指定、子の監護に関する処分についての裁判をする場合には、その子の意見を聞かなければならないとされています。また、15歳未満であっても、裁判所が子の意思を確認することはよくあります。
③母性優先
乳幼児については、特段の事情のない限り、母親の監護を優先させるという考え方です。
④兄弟姉妹不分離
可能な限り、兄弟姉妹の親権者を分けないという考え方です。
養育費
1 養育費とは
養育費とは、未成熟子が社会人として自活するまでに必要な費用をいいます。
親には、子と同居しているか否かに関わらず、自己の経済能力に応じた生活を子にさせる義務があり、子には要求する権利があります。
2 養育費の決定方法
(1)当事者間の話し合い
まず、当事者である夫婦間で話し合い、様々な事情を考慮して、支払額や支払方法等を決定する方法があります。話し合いの結果、支払額等が決定した場合、後日内容について争いになる事態等に備え、書面化しておくのが適切です。強制執行認諾文言付の公正証書を作成しておけば、支払が滞ったとき、強制執行が可能となります。
(2)家庭裁判所の調停・審判等
話し合いで決定することができない場合には、家庭裁判所に調停等を申立てることができます。この場合には、裁判所が両親それぞれの資力等を考慮して適切な額を決定することになります。家庭裁判所での判断がなされた場合、支払が滞ったとき、強制執行が可能となります。
(3)養育費の増減
養育費の額等が一旦決定したとしても後に生じる事情によっては、その額を増減することができる場合があります。この場合も、まずは、話し合いを行うべきですが、話し合いによって結論が出ない場合には、家庭裁判所に対して、養育費の増(減)額請求申立を行うことができます。
財産分与
1 財産分与とは
財産分与請求権とは、離婚した当事者の一方が他方に対し財産の分与を請求する権利をいいます。
2 財産分与の決定時期
財産分与については、離婚時に決定することが多いですが、離婚時に合意できなかった場合等には離婚後に行うことも可能です。ただし、離婚のときから2年経過すると請求できなくなります。
3 財産分与の内容
①婚姻中の夫婦共同財産の精算(精算的財産分与)
②離婚後の扶養(扶養的財産分与)
③離婚による損害賠償(慰謝料的財産分与)
4 精算的財産分与
財産分与の中核と位置づけられてきたのが精算的財産分与です。精算的財産分与の対象となるのは、夫婦が婚姻中に協力して形成・維持してきた共同財産であり、特有財産(一方が婚姻前から所有していた財産や、婚姻中であっても相手方とは無関係に取得した財産)は対象にはなりません。
5 扶養的財産分与
扶養的財産分与は、夫婦財産の清算や慰謝料請求をすることができない、またはそれらを取得しただけでは生計を維持することはできない場合に補充的に認められるものとされており、請求される配偶者に支払の能力があることも必要となりますので、財産分与として常に認められるわけではありません。
6 慰謝料的財産分与
離婚慰謝料についても財産分与に含めることができますが、財産分与とは別に請求することも可能であり、実際には財産分与とは別に請求することが多いと言えます。
慰謝料請求
1 慰謝料とは
相手方の有責行為によってやむを得ず離婚に至った場合、これによって精神的苦痛を被った者は、慰謝料の請求が可能です。
2 慰謝料額の算定
慰謝料額は事案ごとに異なり、精神的苦痛の程度、婚姻期間、当事者の財産状況等を考慮して決定されることになります。
3 慰謝料請求権の消滅時効
慰謝料請求権の性質は不法行為に基づく損害賠償請求権であり、時効期間は、「損害及び加害者を知った時」から3年となります。
【男女問題】
男女問題に関するご相談もお受けしております。このようなお悩みがございましたら、一度ご相談いただければと思います。
・配偶者の不倫相手に慰謝料 を請求したい。
・不倫をしていたら、不倫相手の配偶者から慰謝料を請求された。
・結婚予定だったのに、突然婚約を破棄されてしまった。
・恋人にお金を貸し たが、返してもらえない。